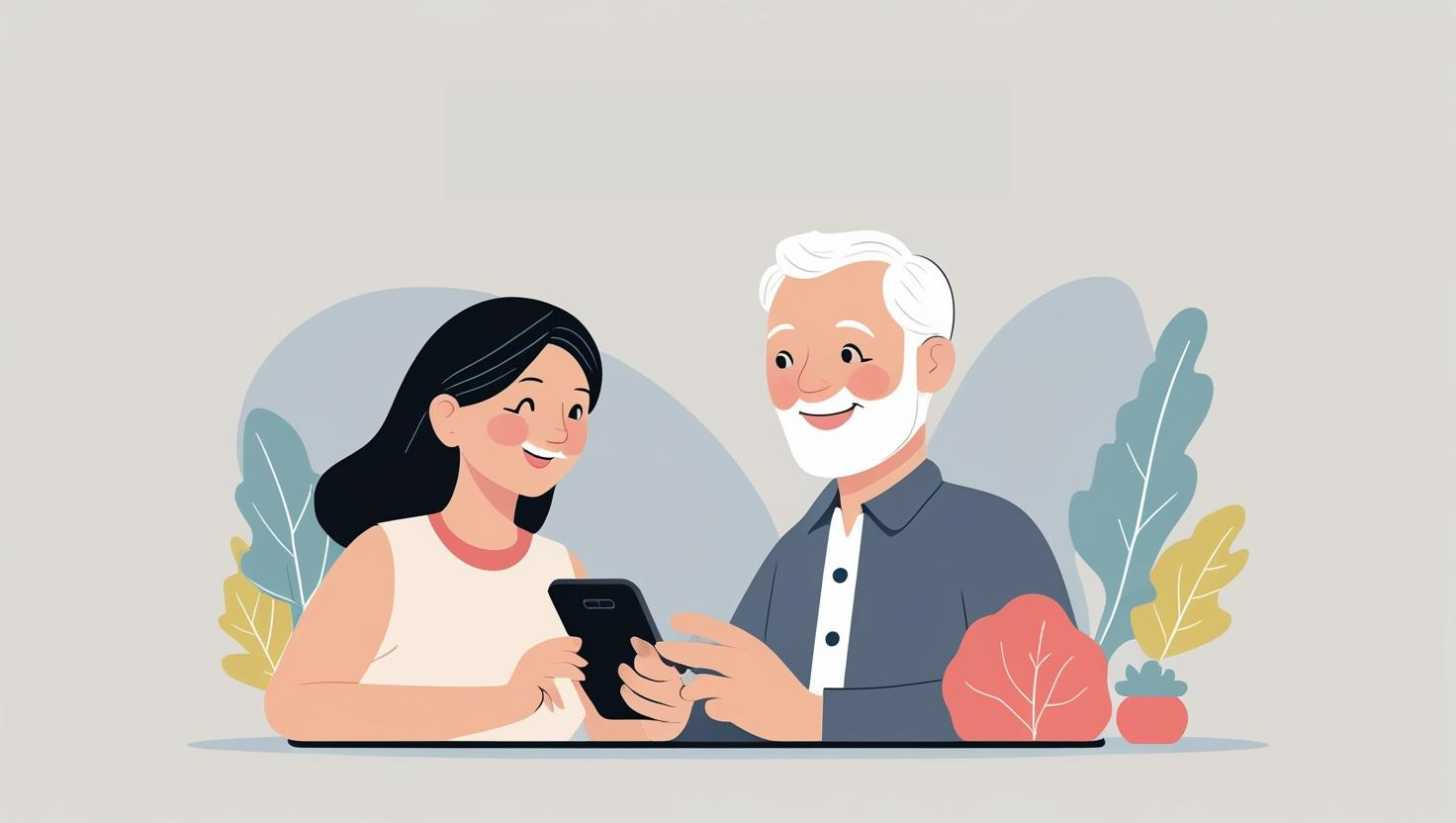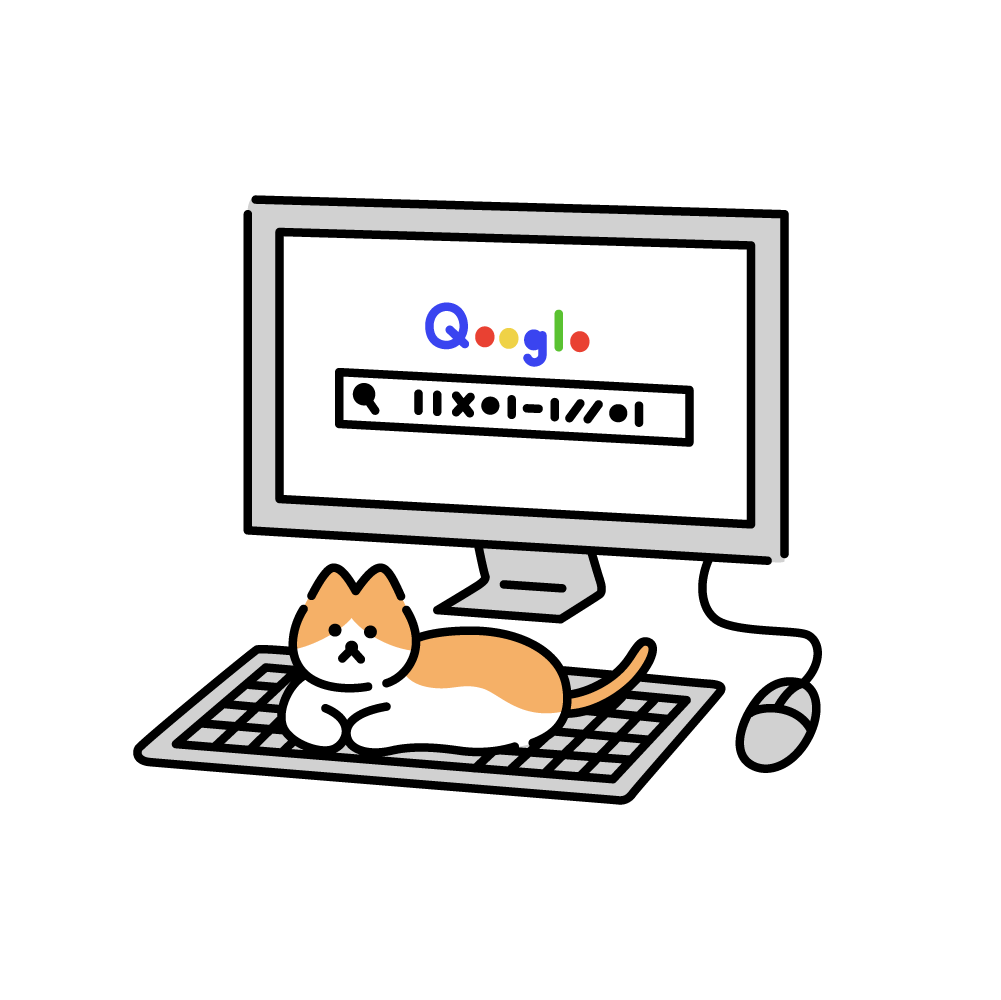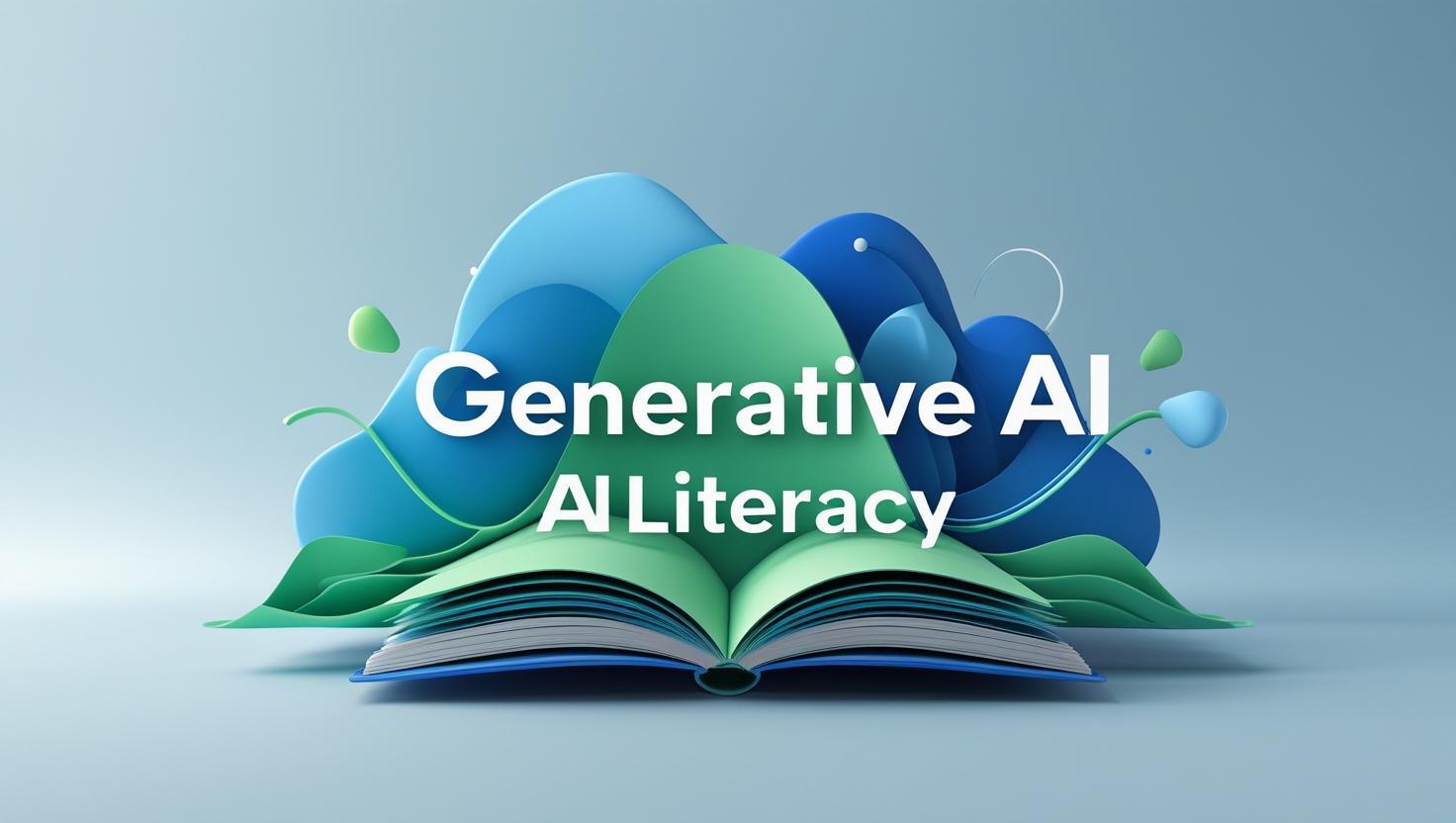ごきげんよう、Sophyです。
暑さも落ち着き、そろそろ秋かな?と思った矢先に、暑さが復活。雨天の日数も増えてきて、湿度の高さに体がついていけません。
さて、今回のブログでは【デジタルデバイド(Digital Divide)】について調べていきたいと思います。サクッと読める内容にしますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです!
デジタルデバイドとは
皆さんは【デジタルデバイド(Digital Divide)】という単語をご存じですか?かく言う私も聞いたことがある程度で、細かいところはわかっていませんでした。
デジタルデバイド(Digital Divide)=情報格差
デジタルデバイド(Digital Divide)は、インターネットやデジタル技術にアクセスできる人とできない人との間に生じる「情報格差」を指します。日常生活や行政手続き、教育、医療、ビジネスなどの様々な場面でデジタル化が進む中、その波に乗りきれない層の人達が社会的・経済的に不利な立場に置かれる現象を指しています。
デジタルデバイドが起こる主な要因
デジタルデバイドの原因は一つではなく、いくつかの要因が複合的に絡み合って発生します。代表的なものを以下に記載します。
1.経済的な要因
デジタル機器やインターネット環境の導入・維持管理には一定の費用が必要です。この費用が障壁となり、環境整備が不十分となります。
2.地域格差による要因
都市部と地方では、高速インターネットや通信インフラの整備状況に格差が生じやすいとされます。また、IT講座等の学習機会の地域差なども要因の一つと考えられます。
3.世代的な要因
若年層と高齢層ではデジタル機器やインターネットに対する知識や操作スキルに大きな違いがあり、高齢者は特に遅れをとりやすい傾向にあります。デジタル機器等に対する苦手意識や不安感が大きな要因の一つであり、周りのサポートが重要となります。
4.教育・知識格差的な要因
基本的なITスキルの不足やセキュリティ意識の低さ、情報の真偽を判断する能力の欠如など、デジタルリテラシーの差が利用格差を生む要因となります。
5.身体的・認知的な要因
認知機能の変化や手指等の身体的制約などの個人の特性により、機器の操作や情報へのアクセスが困難となるケースがあります。
デジタルデバイドがもたらす影響
■教育格差の深刻化
オンライン学習やデジタル教材へのアクセスが制限されることで、教育の質に差が生じる可能性があります。十分な教育が受けられず、将来の選択肢が狭まる可能性も考えられます。
■雇用への影響
デジタルスキルを求められる職種への応募機会の損失や求人情報の収集が困難になるなど、就職活動への影響が考えられます。また、デジタルスキルを持たないことで仕事の幅が限定され、賃金格差が生じる傾向があります。
■情報へのアクセス機会の損失
行政からのお知らせや災害時の情報等を即座に得られないことで、危険回避の行動に遅れが生じる可能性があります。また、ITリテラシーの不足から、情報の信頼性の判断が鈍り、デマに踊らされる可能性も高まります。
上記以外にも、影響がおよぶ場面は多く存在します。デジタル化が進む現代において、取り残さない・取り残されない取組が重要ですね。
デジタルデバイド解消の取組
ここからは、実際の取組を紹介していきます。
【東京都 渋谷区|高齢者デジタルデバイド解消事業】
この取組は、65歳以上の区民で、スマートフォンを保有していない人に、スマートフォンを2年間無料で貸し出し、端末やアプリの活用を支援する実証事業となります。
<事業内容>
1.スマートフォンの貸し出し
2.スマートフォンの活用支援
3.アプリの活用
4.データの収集と分析
実証報告は渋谷区のホームページに記載がありますので、ご参照ください。
参考:渋谷区 高齢者デジタルデバイド解消事業
【神奈川県 藤沢市|スマホ初心者向け講座】
藤沢市では、スマホに興味があるけど使うきっかけがない、使い方がわからないという方向けに、基本操作を学ぶ講座を開催しています。さらに、知識定着のフォローアップとして、ボランティアによる相談会も開催しています。
また、官民連携による取組も実施しており、スマホの基本操作に関する動画の配信やスマホ初心者向けの防災講座等を行っています。
参考:藤沢市 デジタルデバイド対策
最後に
デジタルデバイド解消を目的として、多くの地域でスマホ基礎講座や相談窓口の設置、官民連携による活動など、様々な取組を行っていることがわかりました。
「誰一人取り残されることのないデジタル社会」を目指して、私たちにも何ができるのか、考えていきたいと思います。